シェーン (1953・アメリカ)
■ジャンル: 西部劇
■収録時間: 118分
■スタッフ
監督・製作 : ジョージ・スティーヴンス
原作 : ジャック・シェーファー
脚本 : A・B・ガスリー・Jr
撮影 : ロイヤル・グリッグス
音楽 : ヴィクター・ヤング
■キャスト
アラン・ラッド(シェーン)
ヴァン・ヘフリン(スターレット)
ジーン・アーサー(マリアン)
ブランドン・デ・ワイルド(ジョーイ)
ジャック・パランス(ウィルソン)
ベン・ジョンソン(クリス)
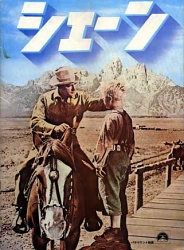
「シェーン、カムバック!」のセリフの響きの美しさと音楽の素晴らしさ。そして、何よりもこのセリフを言う前に一瞬表情が変わるジョーイ少年の愛らしさ。少年の視点で描かれた今尚多くの感情と英知と芸術性を感じさせてくれる知性と感情の泉が本作である。
心の中に本当に響くセリフが数多く存在する映画である。
■あらすじ
西部の大草原に1人の流れ者がやってくる。彼の名はシェーン(アラン・ラッド)。シェーンはスターレット(ヴァン・ヘフリン)一家の下で牧童として働くことになる。黙々と寡黙に働くシェーンの姿に段々と好意を寄せるスターレットの妻マリアン(ジーン・アーサー)とジョーイ少年。そんな中、土地を巡る争いの中でウィルソン(ジャック・パランス)と言う名うてのガンマンが敵対する牧場主に雇われやってきた。シェーンは、堅気の暮らしを諦めスターレット一家の為に立ち上がる。
■遥かなる山の呼び声
ワイオミング州の遙かなる大平原、彼方にはグランド・ティートン山脈の山並みがそびえる。鹿が水を飲み、その鹿にライフルの照準を合わせながら緊張している一人の少年。やがて、鹿と少年は1人の馬上のカウボーイの姿に気づく。もうこのオープニングからして美しすぎる。景色も美しいが、何よりも美しいのは、ヴィクター・ヤングの澄み切った音色である。
『誰が為に鐘は鳴る』(1943)『腰抜け二挺拳銃』(1948)『地上最大のショウ』(1952)『静かなる男』(1952)『大砂塵』(1954)『喝采』(1954)『愛の泉』(1954)『80日間世界一周』(1956)のヴィクター・ヤングによるテーマ曲は「遥かなる山の呼び声(The Call Of The Far Away Hills)」と訳されているが、この訳のセンスが素晴らしい。昔の配給会社の人間は、英語に対するイマジネーションが豊かであった。
ちなみにオープニングに、馬に乗ったシェーンがジョーイの家に向かって大平原を歩いている登場シーンがあるが、シェーンの背後に白いバスが映っている。
■大自然の中、鹿と少年に見守られながら・・・

澄み切った青い目をパチクリさせて馬上の男を見つめる少年。逃げていく鹿、切り株に斧を入れる逞しい父親、民謡を詠いながら家事にいそしむ母親。もうオープニングの2分の描写で1890年のワイオミングにひとっ飛びさせてくれる。この冒頭の映像の組み立て方は、観客をその時代にワープさせる見事な組み立てなのである。ちなみにカメラマン・ロイヤル・グリッグスは本作でアカデミー賞撮影賞カラー部門を受賞している。
スターレットと会話しているシェーンの背後でジョーイ少年がライフル撃鉄をいじる音と同時に、恐るべき程敏捷にその物音に反応し、腰を低く身構えながら振り返り、ホルスターの拳銃に手をかけるシェーン。もうこのワンシーンでこの男は只者ではないと実感させてくれる。そして、その緊張感が彼の実力をいつ見ることが出来るのだろうという期待感を生み出すのである。映画というものは緊張感あふれる説得力のある一つのシーンによって期待感が生み出されるものなのである。このシーンは、昨今の映画が忘れかけている緊張と緩和の法則を伝えてくれている。
■ジーン・アーサーの有終の美

シェーンとスターレットとマリアンという3人の男女の微妙な心の動きが描かれていたことが、この作品にいい影響を与えている。男と男の友情と、男が男を認め合う感情と、夫婦愛と、女としての男に対しての恋慕の感情が複雑に、それでいて気高く交差しているのである。この気高き三角関係ゆえに本作は愛され続けているといっても良いだろう。
シェーンとスターレットが切り株と格闘している手前で、小さな畑に根づけしているジョーイ少年とマリアン。この心地よい自然な構図が本当に見ていて気持ちいのである。そして、当時の入植者の衣装を再現したイーディス・ヘッドもさすがである。
マリアンを演じるジーン・アーサー(1900-1991)は、私が大好きな女優の1人である。フランク・キャプラ作品に出ていたような輝くばかりの美しさは、50代前半の当時は衰えているが、ブロードウェイで着実に磨き上げていた演技力で見事にマリアン役を演じきっている。何よりも彼女の独特の張りのある声音が良い。
ちなみにジョージ・スティーヴンスは彼女のことを「ハリウッドでコメディ・センスがぴか一の女優」と昔から褒め称えていた。そして、本作が彼女の最後の映画出演作品となったのである。セミリタイアしていた彼女が映画出演を一回限りで決意したのもスティーヴンスが監督する作品という理由からである(1942年同監督の『希望の降る街』に主演している)。
一方スターレットを演じたヴァン・ヘフリン(1910-1971)は1942年にマーヴィン・ルロイ監督の『Johnny Eager』でアカデミー助演男優賞を受賞している名優である。
■子を持つ母の悲しい性(さが)
マリアンは寝床のジョーイ少年に諭すように言う。「ジョーイ、シェーンを好きになっては駄目よ」「どうして?」「いつか行ってしまうからよ。悲しいわよ・・・好きになったら」マリアンもシェーンに惹かれ始めていることが分かるシーンである。
子を持つ母というものは、我が子が懐く男性にどうしても惹かれてしまうものらしい。
アラン・ラッド(1913-1964)

アーカンソー州出身。代表作は『シェーン』(1953)『マッコーネル物語』(1955)『島の女』(1957)。身長は165㎝と公表されているが160弱らしい。凄まじい極貧の家庭に生まれ幼少期に父を亡くし、さらに5歳のときに住んでいたアパートまで全焼し焼け出される。家計を助けるために8歳頃からフルーツ・ピッキング、新聞売り等を始める。高校時代はダイビングの選手として活躍しオリンピック出場まで考えたほどであった。
売れない俳優だった1936年結婚する。このすぐ後にアルコール中毒の母親が、殺虫剤を使用し自殺した死体を数ヵ月後に発見してしまう。1941年には小さな役で『市民ケーン』にも出演している。1942年スー・キャロル(1906-1982)と再婚し、この年『拳銃貸します』でスターに。兵役を終えたその後ワーナーと契約し、パラマウントで残りの契約を消化中の1953年『シェーン』に出演してこれが大ヒット。
しかし、これが唯一の代表作となって以降は人気が低迷する。元々情緒不安定だったので極度のアルコール依存症に陥るようになる。1962年には拳銃による自殺未遂を起こし、1964年に薬物とアルコールの乱用によりパーム・スプリングスの別荘で死亡している所を発見された。1961年にインタビューで「もしあなたの何かが変えられるとしたら何を変えたいですか?」と質問され「すべて」と冷たく言い放ったという。結婚は2回で前妻との子供、アラン・ラッド・Jrは後に20世紀FOX社長として『スター・ウォーズ』誕生の影の功労者となる。(写真はマリリン・モンローと。1954年)
■ジャック・パランス
ジャック・パランス(1919-2006)
ウクライナ系移民でペンシルバニア出身である。炭坑夫の父と共に炭坑で働く。1940年代前半には、ヘビー級のプロボクサーとなり、第二次世界大戦中は爆撃機パイロットとして従軍。演習中に火傷を負って顔にプラスティック整形手術を受けている。大戦後にスタンフォード大学で演劇を学んび、1950年映画デビューし、本作ではアカデミー助演男優賞にノミネートされた。代表作は『暗黒の恐怖』(1950)『攻撃』(1956)『軽蔑』(1963)『バグダッド・カフェ』(1987)『シティ・スリッカーズ』(1991・アカデミー助演男優賞受賞)。
オスカーを受賞したときに、まだまだ若い役者には負けてないよと苦笑いしながら受賞スピーチ中にステージ上で片腕たて伏せしたことは今も語り継がれる伝説となっている。彼はまた決して自分の出演した作品を見なかったという。ウクライナ語、ロシア語、フランス語、イタリア語、スペイン語、英語を話せた。
そんなジャック・パランス演じる黒ずくめの殺し屋ウィルソンが、馬にとぼとぼ揺られながら登場する。実際それまでパランスは馬に乗ったことが無かったため颯爽とした登場ではなくとぼとぼと登場するシーンになったのではあるが、この変に余裕綽綽の登場シーンが結果的にはウィルソンらしい不敵さをかもし出すこととなった。
■シェーンの拳銃の腕
シェーンは、ジョーイにねだられ拳銃の腕を披露することになる。このショットはかなり緊張感あふれるシーンで、それゆえに実際に石ころを撃ったのは無名時代のジェームス・ディーンだという作り話まで流布したほどである。実際のところこのシーンのためにラッド自身が119回テイクを重ねたという。
そして、ジョーイの前で射撃を見せたシェーンを咎めたマリアンに言う。「銃はただの道具だ。斧やスコップと同じように使う人間次第で良くも悪くもなる」それに対して言い放つマリアンのセリフが良い。「銃なんて一丁も無ければみんなが幸せに暮らせるのに・・あなたの銃も含めて」このセリフは現在のアメリカ社会においても尚生々しい切実なるセリフだろう。
■ここから急速に西部劇が暴力へ傾斜し始めた
本作にはエライシャ・クックJr(1902-1995)『マルタの鷹』(1941)『三つ数えろ』(1946)『現金に体を張れ』(1956)『片目のジャック』(1960)『ローズマリーの赤ちゃん』(1968))が出演している。「ハリウッド一こすい男」が似合う俳優であり、ある意味ハリウッド版川谷拓三でもあるクックが今回も壮絶な死に様を見せてくれる。ウィルソンに笑みを浮かべながら撃ち殺されて泥沼の中に吹っ飛んでいくのである。
サム・ペキンパーは語っている。「ジャック・パランスが酒場の前でエリシャ・クック・ジュニアの農夫を射殺する時のショッキングな銃声が西部劇の歴史を変えた。ここから急速に西部劇が暴力へ傾斜し始めた」
最後にライカー達の企みを知らせに来るクリスがとても良い。ジョン・フォード作品の常連ベン・ジョンソンが演じているのだが、前半においてシェーンと殴り合いの喧嘩をしたにもかかわらず、ここで和解の握手をするシーンがすがすがしい。ちなみに原作ではシェーンが去った後、彼がスターレットに雇われることになるのである。
この作品においてクリスは実に地味ながら魅力的な役柄を演じているのである。最初のほうの登場シーンにおいて帽子をショッピングしている女性の鏡越しの姿を眺めている。やがてその女性に眺めていることに気づかれ照れ笑いをして見せるが、そっぽを向かれた後の実に悲しげな表情。その表情がこいつはそれほど悪いやつではないのだと教えてくれているのである。
しかし、スティーヴンスは根っからの完璧主義者なので一つ一つの映像の中に色々なスパイスが味付けされているのである。何回も見れば見るほどよりその作品の奥深さを堪能できるということは芸術の最も重要な要素の一つであろう。
■西部劇の醍醐味


ライカーと死を覚悟して話をつけに行こうとするスターレットを止めるために殴り合いの喧嘩をするシェーン。殴り合っても殴り合っても終わりのない殴り合いに終止符を打つためにやむを得ずジョーを銃把で殴って気絶させ、スターレット家に永い別れを告げて自分が町へ出かける。
その時に銃で父スターレットを殴りつけたシェーンを見てジョニー少年は「銃で殴ったな。大嫌いだよ」と言うのだが、この時のシェーンの表情の悲しいこと悲しいこと。そして、シェーンはマリアンに言う。私が行くと・・・マリアンは引きとめながら言う。「銃は捨てたんでしょ」「気が変った」「私のため?」「そうあなたと・・・君ら家族のためさ」マリアンはシェーンを見つめ悲しそうな表情でゆっくりと「決して・・・死なないでね」と言って別れの握手をする。そして、シェーンが去った後、シェーンが銃で父を殴った意味を悟ったジョニー少年はシェーンを追いかける。
ラストのウィルソンとの一対一の撃ちあいは映画史上に残る文句なしに素晴らしい決闘シーンである。一瞬で勝負が決まるところがまた良い。しかも、後ろのほうに吹っ飛んで倒れていくウィルソンのやられ方の爽快さ。アラン・ラッドはスティーブンス監督の要求で銃の早撃ちを習得し、このシーン銃を抜いて撃つまでの時間はわずか0.6秒。これは映画史上最速の早撃ち記録といわれている。
■ジョニー坊やとシェーン


ジョニー「すごいや!勝つと思ってたよ。相手はウィルソンだったの?」
シェーン「ああ、ウィルソンだった。すご腕の早撃ちだった」
シェーン「お別れだ、人間は自分の器を破ることは出来ない。頑張ったが駄目だった」
ジョニー「居てほしいよ」
シェーン「一度でも人を殺せば、あと戻りは出来ないんだ。その烙印からは一生逃げられない。帰ってママに言えよ。もう安心しろ。もう銃はないと」
ジョニー「シェーン。血が出ているよ・・・」
シェーン「何てことない。さあ家に帰るんだ。真っ直ぐで強い男になれよ。パパとママを大事にするんだぞ」
最後のジョニー少年との別れのシェーンの言葉がまた良い。
この作品が永遠の輝きを保つ要因を持ちえた理由は明確に、少年の視点でガンマンの戦いを描いた点にあるだろう。ブランドン・デ・ワイルド(1942-1972)は1952年にフレッド・ジンネマン監督の『結婚式の参列者』でデビューしているが、作品自体は失敗作だった。しかし、本作ではアカデミー助演男優賞にノミネートされた。彼は1972年にバイク事故で30歳の若さで死亡する。代表作『ハッド』(1962)。
このジョーイ少年は、最初は結構小生意気な少年にしか見えないのだが、段々と可愛らしく感じてくるのである。こういった感情がこの少年に湧き上がってくるのも、スティーヴンスの隙のない少年の視点による物語が大人にも受け止めやすいように構成されているが所以だろう。
■さまざまな憶測が飛ぶ伝説のラストシーン

特にシェーンがジョーイに最後の言葉を放ってから「シェーン・カムバック!」のラストまでの余韻が素晴らしい。音楽と少年のセリフのエコーが見事な協奏曲的要素をかもし出しているのである。この組み合わせは相当に芸術的であり神々しい。その声に対して去っていくシェーンは決して振り返らない。そして、墓地を通り過ぎていき映画は終わる。この描写がシェーンの死を意味していることは明確であるが、それが肉体的な死を意味するのか彼のガンマンとしての生き様の死を意味するのかは人それぞれの捉え方だろう。ただ一つだけ重要なことは、シェーンがどれだけ時代から取り残された生き方をしていたとしても、少年の心の中には重要なメッセージを残して生き続けたという点である。

つまり、孤独だったガンマンが、初めてジョニーという少年と出会った事によって孤独ではない瞬間があったということを見ている側は思い出すのである。そのことによって孤独の旅に旅立っていくシェーンの胸のうちを無意識のうちに考え、感動するのである。実は本作はジョニーがシェーンと別れる悲しみによって見ている側の胸を打っているのではなく、生まれて初めて孤独から解き放たれたシェーンが再び孤独の旅に旅立っていく姿に胸を打たれているのである。
ちなみに『交渉人』(1998)においても、シェーンは実は最後に死んでいるんだというサミュエル・L・ジャクソンのセリフがある。ちなみに松田優作主演の『蘇える金狼』(1979)の原作とは全く違うラストは優作がこの映画のラストに触発されて考え出したという。
男が去るときは、決して後ろを振り返らずに去る。この映画が日本の50年代後半から60年代の日活映画と東映任侠映画に与えた影響は計り知れないのである。
当初ジョージ・スティーヴンスはシェーン役に『陽のあたる場所』(1951)で主役をつとめたモンゴメリー・クリフトを考えていたが、『地上より永遠に』(1953)に出演することにより断られた。一方、スターレット役をウィリアム・ホールデンに依頼したがこれも断られている。さらにマリオン役は当初キャサリン・ヘップバーンで考えていたという。
本作は1951年の秋にはすでに撮影終了していたが、完璧主義者のスティーヴンスは約一年かけて編集したという。ちなみにパラマウントはこの作品が完成した後、制作費を回収することは不可能だと計算していたが、結果的に制作費を遥かに超える利益を生み出したという。
本作は1953年に日本初公開され、1962、1970、1973、1975年にリバイバル上映されている。
- 2007年5月7日 -
■ジャンル: 西部劇
■収録時間: 118分
■スタッフ
監督・製作 : ジョージ・スティーヴンス
原作 : ジャック・シェーファー
脚本 : A・B・ガスリー・Jr
撮影 : ロイヤル・グリッグス
音楽 : ヴィクター・ヤング
■キャスト
アラン・ラッド(シェーン)
ヴァン・ヘフリン(スターレット)
ジーン・アーサー(マリアン)
ブランドン・デ・ワイルド(ジョーイ)
ジャック・パランス(ウィルソン)
ベン・ジョンソン(クリス)
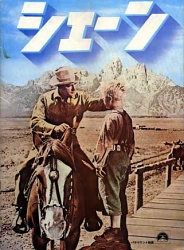
「シェーン、カムバック!」のセリフの響きの美しさと音楽の素晴らしさ。そして、何よりもこのセリフを言う前に一瞬表情が変わるジョーイ少年の愛らしさ。少年の視点で描かれた今尚多くの感情と英知と芸術性を感じさせてくれる知性と感情の泉が本作である。
心の中に本当に響くセリフが数多く存在する映画である。
■あらすじ
西部の大草原に1人の流れ者がやってくる。彼の名はシェーン(アラン・ラッド)。シェーンはスターレット(ヴァン・ヘフリン)一家の下で牧童として働くことになる。黙々と寡黙に働くシェーンの姿に段々と好意を寄せるスターレットの妻マリアン(ジーン・アーサー)とジョーイ少年。そんな中、土地を巡る争いの中でウィルソン(ジャック・パランス)と言う名うてのガンマンが敵対する牧場主に雇われやってきた。シェーンは、堅気の暮らしを諦めスターレット一家の為に立ち上がる。
■遥かなる山の呼び声
ワイオミング州の遙かなる大平原、彼方にはグランド・ティートン山脈の山並みがそびえる。鹿が水を飲み、その鹿にライフルの照準を合わせながら緊張している一人の少年。やがて、鹿と少年は1人の馬上のカウボーイの姿に気づく。もうこのオープニングからして美しすぎる。景色も美しいが、何よりも美しいのは、ヴィクター・ヤングの澄み切った音色である。
『誰が為に鐘は鳴る』(1943)『腰抜け二挺拳銃』(1948)『地上最大のショウ』(1952)『静かなる男』(1952)『大砂塵』(1954)『喝采』(1954)『愛の泉』(1954)『80日間世界一周』(1956)のヴィクター・ヤングによるテーマ曲は「遥かなる山の呼び声(The Call Of The Far Away Hills)」と訳されているが、この訳のセンスが素晴らしい。昔の配給会社の人間は、英語に対するイマジネーションが豊かであった。
ちなみにオープニングに、馬に乗ったシェーンがジョーイの家に向かって大平原を歩いている登場シーンがあるが、シェーンの背後に白いバスが映っている。
■大自然の中、鹿と少年に見守られながら・・・

澄み切った青い目をパチクリさせて馬上の男を見つめる少年。逃げていく鹿、切り株に斧を入れる逞しい父親、民謡を詠いながら家事にいそしむ母親。もうオープニングの2分の描写で1890年のワイオミングにひとっ飛びさせてくれる。この冒頭の映像の組み立て方は、観客をその時代にワープさせる見事な組み立てなのである。ちなみにカメラマン・ロイヤル・グリッグスは本作でアカデミー賞撮影賞カラー部門を受賞している。
スターレットと会話しているシェーンの背後でジョーイ少年がライフル撃鉄をいじる音と同時に、恐るべき程敏捷にその物音に反応し、腰を低く身構えながら振り返り、ホルスターの拳銃に手をかけるシェーン。もうこのワンシーンでこの男は只者ではないと実感させてくれる。そして、その緊張感が彼の実力をいつ見ることが出来るのだろうという期待感を生み出すのである。映画というものは緊張感あふれる説得力のある一つのシーンによって期待感が生み出されるものなのである。このシーンは、昨今の映画が忘れかけている緊張と緩和の法則を伝えてくれている。
■ジーン・アーサーの有終の美

シェーンとスターレットとマリアンという3人の男女の微妙な心の動きが描かれていたことが、この作品にいい影響を与えている。男と男の友情と、男が男を認め合う感情と、夫婦愛と、女としての男に対しての恋慕の感情が複雑に、それでいて気高く交差しているのである。この気高き三角関係ゆえに本作は愛され続けているといっても良いだろう。
シェーンとスターレットが切り株と格闘している手前で、小さな畑に根づけしているジョーイ少年とマリアン。この心地よい自然な構図が本当に見ていて気持ちいのである。そして、当時の入植者の衣装を再現したイーディス・ヘッドもさすがである。
マリアンを演じるジーン・アーサー(1900-1991)は、私が大好きな女優の1人である。フランク・キャプラ作品に出ていたような輝くばかりの美しさは、50代前半の当時は衰えているが、ブロードウェイで着実に磨き上げていた演技力で見事にマリアン役を演じきっている。何よりも彼女の独特の張りのある声音が良い。
ちなみにジョージ・スティーヴンスは彼女のことを「ハリウッドでコメディ・センスがぴか一の女優」と昔から褒め称えていた。そして、本作が彼女の最後の映画出演作品となったのである。セミリタイアしていた彼女が映画出演を一回限りで決意したのもスティーヴンスが監督する作品という理由からである(1942年同監督の『希望の降る街』に主演している)。
一方スターレットを演じたヴァン・ヘフリン(1910-1971)は1942年にマーヴィン・ルロイ監督の『Johnny Eager』でアカデミー助演男優賞を受賞している名優である。
■子を持つ母の悲しい性(さが)
マリアンは寝床のジョーイ少年に諭すように言う。「ジョーイ、シェーンを好きになっては駄目よ」「どうして?」「いつか行ってしまうからよ。悲しいわよ・・・好きになったら」マリアンもシェーンに惹かれ始めていることが分かるシーンである。
子を持つ母というものは、我が子が懐く男性にどうしても惹かれてしまうものらしい。
アラン・ラッド(1913-1964)

アーカンソー州出身。代表作は『シェーン』(1953)『マッコーネル物語』(1955)『島の女』(1957)。身長は165㎝と公表されているが160弱らしい。凄まじい極貧の家庭に生まれ幼少期に父を亡くし、さらに5歳のときに住んでいたアパートまで全焼し焼け出される。家計を助けるために8歳頃からフルーツ・ピッキング、新聞売り等を始める。高校時代はダイビングの選手として活躍しオリンピック出場まで考えたほどであった。
売れない俳優だった1936年結婚する。このすぐ後にアルコール中毒の母親が、殺虫剤を使用し自殺した死体を数ヵ月後に発見してしまう。1941年には小さな役で『市民ケーン』にも出演している。1942年スー・キャロル(1906-1982)と再婚し、この年『拳銃貸します』でスターに。兵役を終えたその後ワーナーと契約し、パラマウントで残りの契約を消化中の1953年『シェーン』に出演してこれが大ヒット。
しかし、これが唯一の代表作となって以降は人気が低迷する。元々情緒不安定だったので極度のアルコール依存症に陥るようになる。1962年には拳銃による自殺未遂を起こし、1964年に薬物とアルコールの乱用によりパーム・スプリングスの別荘で死亡している所を発見された。1961年にインタビューで「もしあなたの何かが変えられるとしたら何を変えたいですか?」と質問され「すべて」と冷たく言い放ったという。結婚は2回で前妻との子供、アラン・ラッド・Jrは後に20世紀FOX社長として『スター・ウォーズ』誕生の影の功労者となる。(写真はマリリン・モンローと。1954年)
■ジャック・パランス
ジャック・パランス(1919-2006)
ウクライナ系移民でペンシルバニア出身である。炭坑夫の父と共に炭坑で働く。1940年代前半には、ヘビー級のプロボクサーとなり、第二次世界大戦中は爆撃機パイロットとして従軍。演習中に火傷を負って顔にプラスティック整形手術を受けている。大戦後にスタンフォード大学で演劇を学んび、1950年映画デビューし、本作ではアカデミー助演男優賞にノミネートされた。代表作は『暗黒の恐怖』(1950)『攻撃』(1956)『軽蔑』(1963)『バグダッド・カフェ』(1987)『シティ・スリッカーズ』(1991・アカデミー助演男優賞受賞)。
オスカーを受賞したときに、まだまだ若い役者には負けてないよと苦笑いしながら受賞スピーチ中にステージ上で片腕たて伏せしたことは今も語り継がれる伝説となっている。彼はまた決して自分の出演した作品を見なかったという。ウクライナ語、ロシア語、フランス語、イタリア語、スペイン語、英語を話せた。
そんなジャック・パランス演じる黒ずくめの殺し屋ウィルソンが、馬にとぼとぼ揺られながら登場する。実際それまでパランスは馬に乗ったことが無かったため颯爽とした登場ではなくとぼとぼと登場するシーンになったのではあるが、この変に余裕綽綽の登場シーンが結果的にはウィルソンらしい不敵さをかもし出すこととなった。
■シェーンの拳銃の腕
シェーンは、ジョーイにねだられ拳銃の腕を披露することになる。このショットはかなり緊張感あふれるシーンで、それゆえに実際に石ころを撃ったのは無名時代のジェームス・ディーンだという作り話まで流布したほどである。実際のところこのシーンのためにラッド自身が119回テイクを重ねたという。
そして、ジョーイの前で射撃を見せたシェーンを咎めたマリアンに言う。「銃はただの道具だ。斧やスコップと同じように使う人間次第で良くも悪くもなる」それに対して言い放つマリアンのセリフが良い。「銃なんて一丁も無ければみんなが幸せに暮らせるのに・・あなたの銃も含めて」このセリフは現在のアメリカ社会においても尚生々しい切実なるセリフだろう。
■ここから急速に西部劇が暴力へ傾斜し始めた
本作にはエライシャ・クックJr(1902-1995)『マルタの鷹』(1941)『三つ数えろ』(1946)『現金に体を張れ』(1956)『片目のジャック』(1960)『ローズマリーの赤ちゃん』(1968))が出演している。「ハリウッド一こすい男」が似合う俳優であり、ある意味ハリウッド版川谷拓三でもあるクックが今回も壮絶な死に様を見せてくれる。ウィルソンに笑みを浮かべながら撃ち殺されて泥沼の中に吹っ飛んでいくのである。
サム・ペキンパーは語っている。「ジャック・パランスが酒場の前でエリシャ・クック・ジュニアの農夫を射殺する時のショッキングな銃声が西部劇の歴史を変えた。ここから急速に西部劇が暴力へ傾斜し始めた」
最後にライカー達の企みを知らせに来るクリスがとても良い。ジョン・フォード作品の常連ベン・ジョンソンが演じているのだが、前半においてシェーンと殴り合いの喧嘩をしたにもかかわらず、ここで和解の握手をするシーンがすがすがしい。ちなみに原作ではシェーンが去った後、彼がスターレットに雇われることになるのである。
この作品においてクリスは実に地味ながら魅力的な役柄を演じているのである。最初のほうの登場シーンにおいて帽子をショッピングしている女性の鏡越しの姿を眺めている。やがてその女性に眺めていることに気づかれ照れ笑いをして見せるが、そっぽを向かれた後の実に悲しげな表情。その表情がこいつはそれほど悪いやつではないのだと教えてくれているのである。
しかし、スティーヴンスは根っからの完璧主義者なので一つ一つの映像の中に色々なスパイスが味付けされているのである。何回も見れば見るほどよりその作品の奥深さを堪能できるということは芸術の最も重要な要素の一つであろう。
■西部劇の醍醐味


ライカーと死を覚悟して話をつけに行こうとするスターレットを止めるために殴り合いの喧嘩をするシェーン。殴り合っても殴り合っても終わりのない殴り合いに終止符を打つためにやむを得ずジョーを銃把で殴って気絶させ、スターレット家に永い別れを告げて自分が町へ出かける。
その時に銃で父スターレットを殴りつけたシェーンを見てジョニー少年は「銃で殴ったな。大嫌いだよ」と言うのだが、この時のシェーンの表情の悲しいこと悲しいこと。そして、シェーンはマリアンに言う。私が行くと・・・マリアンは引きとめながら言う。「銃は捨てたんでしょ」「気が変った」「私のため?」「そうあなたと・・・君ら家族のためさ」マリアンはシェーンを見つめ悲しそうな表情でゆっくりと「決して・・・死なないでね」と言って別れの握手をする。そして、シェーンが去った後、シェーンが銃で父を殴った意味を悟ったジョニー少年はシェーンを追いかける。
ラストのウィルソンとの一対一の撃ちあいは映画史上に残る文句なしに素晴らしい決闘シーンである。一瞬で勝負が決まるところがまた良い。しかも、後ろのほうに吹っ飛んで倒れていくウィルソンのやられ方の爽快さ。アラン・ラッドはスティーブンス監督の要求で銃の早撃ちを習得し、このシーン銃を抜いて撃つまでの時間はわずか0.6秒。これは映画史上最速の早撃ち記録といわれている。
■ジョニー坊やとシェーン


ジョニー「すごいや!勝つと思ってたよ。相手はウィルソンだったの?」
シェーン「ああ、ウィルソンだった。すご腕の早撃ちだった」
シェーン「お別れだ、人間は自分の器を破ることは出来ない。頑張ったが駄目だった」
ジョニー「居てほしいよ」
シェーン「一度でも人を殺せば、あと戻りは出来ないんだ。その烙印からは一生逃げられない。帰ってママに言えよ。もう安心しろ。もう銃はないと」
ジョニー「シェーン。血が出ているよ・・・」
シェーン「何てことない。さあ家に帰るんだ。真っ直ぐで強い男になれよ。パパとママを大事にするんだぞ」
最後のジョニー少年との別れのシェーンの言葉がまた良い。
この作品が永遠の輝きを保つ要因を持ちえた理由は明確に、少年の視点でガンマンの戦いを描いた点にあるだろう。ブランドン・デ・ワイルド(1942-1972)は1952年にフレッド・ジンネマン監督の『結婚式の参列者』でデビューしているが、作品自体は失敗作だった。しかし、本作ではアカデミー助演男優賞にノミネートされた。彼は1972年にバイク事故で30歳の若さで死亡する。代表作『ハッド』(1962)。
このジョーイ少年は、最初は結構小生意気な少年にしか見えないのだが、段々と可愛らしく感じてくるのである。こういった感情がこの少年に湧き上がってくるのも、スティーヴンスの隙のない少年の視点による物語が大人にも受け止めやすいように構成されているが所以だろう。
■さまざまな憶測が飛ぶ伝説のラストシーン

特にシェーンがジョーイに最後の言葉を放ってから「シェーン・カムバック!」のラストまでの余韻が素晴らしい。音楽と少年のセリフのエコーが見事な協奏曲的要素をかもし出しているのである。この組み合わせは相当に芸術的であり神々しい。その声に対して去っていくシェーンは決して振り返らない。そして、墓地を通り過ぎていき映画は終わる。この描写がシェーンの死を意味していることは明確であるが、それが肉体的な死を意味するのか彼のガンマンとしての生き様の死を意味するのかは人それぞれの捉え方だろう。ただ一つだけ重要なことは、シェーンがどれだけ時代から取り残された生き方をしていたとしても、少年の心の中には重要なメッセージを残して生き続けたという点である。

つまり、孤独だったガンマンが、初めてジョニーという少年と出会った事によって孤独ではない瞬間があったということを見ている側は思い出すのである。そのことによって孤独の旅に旅立っていくシェーンの胸のうちを無意識のうちに考え、感動するのである。実は本作はジョニーがシェーンと別れる悲しみによって見ている側の胸を打っているのではなく、生まれて初めて孤独から解き放たれたシェーンが再び孤独の旅に旅立っていく姿に胸を打たれているのである。
ちなみに『交渉人』(1998)においても、シェーンは実は最後に死んでいるんだというサミュエル・L・ジャクソンのセリフがある。ちなみに松田優作主演の『蘇える金狼』(1979)の原作とは全く違うラストは優作がこの映画のラストに触発されて考え出したという。
男が去るときは、決して後ろを振り返らずに去る。この映画が日本の50年代後半から60年代の日活映画と東映任侠映画に与えた影響は計り知れないのである。
当初ジョージ・スティーヴンスはシェーン役に『陽のあたる場所』(1951)で主役をつとめたモンゴメリー・クリフトを考えていたが、『地上より永遠に』(1953)に出演することにより断られた。一方、スターレット役をウィリアム・ホールデンに依頼したがこれも断られている。さらにマリオン役は当初キャサリン・ヘップバーンで考えていたという。
本作は1951年の秋にはすでに撮影終了していたが、完璧主義者のスティーヴンスは約一年かけて編集したという。ちなみにパラマウントはこの作品が完成した後、制作費を回収することは不可能だと計算していたが、結果的に制作費を遥かに超える利益を生み出したという。
本作は1953年に日本初公開され、1962、1970、1973、1975年にリバイバル上映されている。
- 2007年5月7日 -